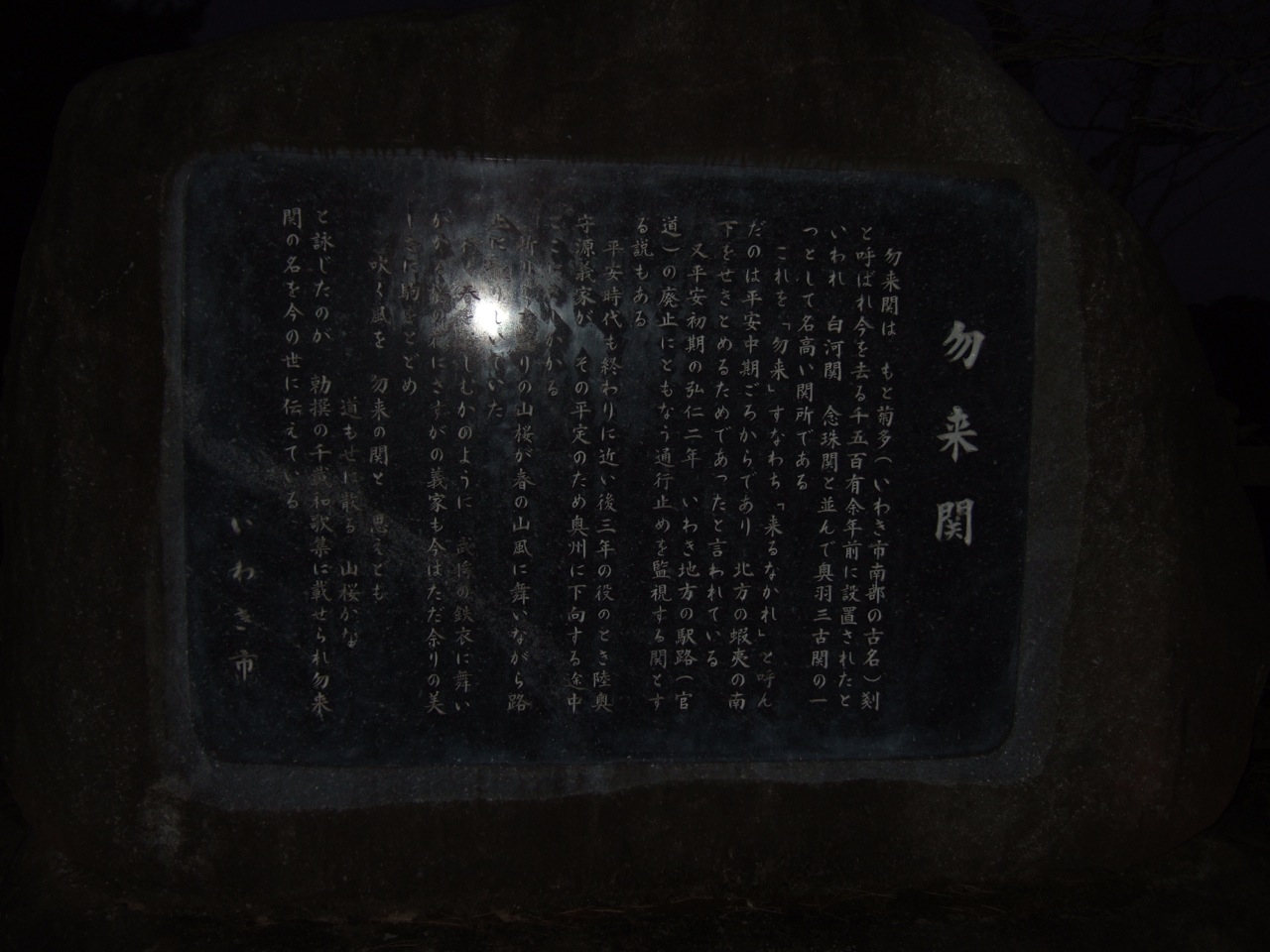宮下康仁『青春への遺書:新しく出発ためのさらば青春の手記』(ルック社 1973)を読む。
学生時代にぼろぼろの状態で手に入れたものなので、読みながらどんどんページが抜けていってしまった。
執筆当時早稲田大学4年生であった著者が、西荻窪にある都立西高校から駿台予備校、そして早稲田大学に至るまでの友人との交流記である。学校のことや酒、女性だけでなく、受験体制や学生運動まで話は広がっていく。個人の悩みを社会に訴えたり、社会の矛盾が個人の悩みとなるなど、社会と個人がべったりと密接していた時代状況を感じ取ることができた。
高校3年生になって受験を意識するようになり、著者の宮下君は次のような感想を漏らしている。
東大では全学バリケード封鎖へと闘争スローガンが変わり、反日共系の学生の間で対立が激しくなっていった。東大とは、日本 資本主義のいつも最先端にある建物だ。一年生の頃、三四郎池で藤棚を眺め、広い広い学内を散歩していた。あの時の東大は今、もうないんだ。大学解体という 恐ろしい言葉。いつの時代も叫ぶことのなかった大学解体という言葉。大学生は大学生でしかなかったし、いつも問題は自分の外側にある環境だった。学問のあるものが外側の世界を冷静な目でみつめ、教授たちとなごやかに微笑しあっていた。決して自己の内部世界まで壊そうとはだれも気がつかなかった。そして今、赤いレンガが崩れようとしているのだ。自分がこうしてここに居ていいのだろうか。--。自分が加害者であることに気がついたとき、吐き気よりすざましく吐き続ける。早くこの身体の中に貯えたものをピョンピョン取り出して捨てちまぇ。
また、西高の卒業式を巡っての「ぼやき」の一節が印象に残った。極めて「ノンセクト・ラジカル」的な発想である。
ふと思う。やっぱり予期できない瞬間をつくり上げなくちゃ、日常という連続は断ち切れないんだと。