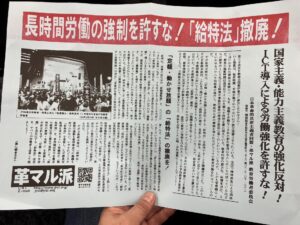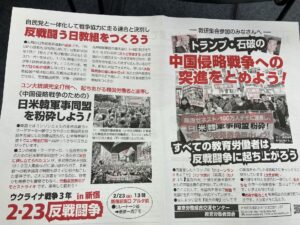河相一成『食卓から見た日本の食糧』(新日本新書,1986)を読む。
食糧自給率の低下とそれに伴う日本の農業の没落、そしてあるべき食生活について論じられている。当時はなかっただろうが、いわゆる「食糧安全保障」についての著書である。
日本の食糧自給率がどのように低下していったのかについての論が興味深かった。1954年3月に日本国とアメリカ合衆国との間で相互防衛援助協定(日米Mutual Security Act MSA協定)が締結されたが、実は同時に日本の経済の安定という名目で「MSA小麦協定」が結ばれていたのだ。この協定にそって、1955年、1956年にわたって米国の余剰農産物を受け入れることになる。受け入れ量は小麦が80万トン、大麦が15万5000トン、飼料が11万トン、綿花が27万5000俵となっている。
また、これに合わせて1954年に「学校給食法」が制定されている。その時の文部大臣の提案理由には「今後の国民食生活は粉食混合形態が必要だが、米食偏重是正はなかなか困難なため、学校給食により幼少時代に教育的に配慮された合理的な食事に慣れさせる」として、米飯からパン等への切り替えが強引になされた。
さらに1956年から数年間にわたって、厚生省の外郭団体のキッチンカーが全国隅々まで走り、主婦を集めて、パンやスパゲティ、ケーキなどを作ってみせて試食させる普及事業が展開された。また、「米を食べるとバカになる」「米を食べると美容に悪い」といった宣伝までまことしやかに流布された。著書は次のように述べる。
これらのキャンペーンの陰にアメリカの余剰小麦市場開拓の黒い意図があることを国民が知っていたなら、そう簡単に宣伝にのせられることはなかったのではないでしょうか。そういう意味でアメリカの小麦市場開拓の戦略は知能犯罪な完全犯罪を押し通したことになります。加えて、その完全犯罪に手を貸した日本政府や一部の学者は、共犯者としての罪を負うべきでしょう。
では、国内の小麦農家が増えたのかというと、そこにも巧妙な戦略が見え隠れする。当時の食糧管理制度のもとで、小麦の価格も政府が決めることになっていたが、この水準が低く抑えられ、麦作農民経営の採算に合わず、麦生産から農民は離れていくことになった。1960年には国内で380万トンの麦が生産されていたが、1984年にはわずか110万トンにまで激減することになった。いかに日本の農業が米国や日本政府によって歪められてきたのかという証しである。
良書であった。著者は4年前に亡くなっているが、晩年まで憲法9条や食糧問題について論じられている。