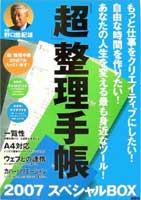一年も半分を過ぎてから、今年度の手帳を買い直した。ここ3年ほど、2穴リフィルや、A5サイズの6穴リフィルのシステム手帳を使っていたが、高校に移ってからはどうも使い勝手が悪いと感じていた。日常デスクワークが主体で、常に目の前にメモ帳やファイルがあるにも関わらず、分厚いシステム手帳を開くのはあまり非効率であり、だいいち億劫である。特に4月以降は義理で色々と書き込んでいたが、正直携帯電話のカレンダー機能の方が使い勝手がよく、無用の長物と成り果てていた。
ということで、数年前に使っていた「超」整理手帳に戻ることになった。運よく1冊だけアマゾンに在庫があったのですぐに「ポチッ」としてしまった。ポストイットやメモ帳、ToDoリストを使いこなし、ばりばりのビジネスマンよろしくスケジュール管理を行ってみたい。手帳を使うことで余計に仕事や家族に忙殺されるのではなく、読書や映画といった有意義な「暇」な時間を創り出していきたいと思う。
「学習・学び」カテゴリーアーカイブ
社会福祉学
正月休みに入って少しずつ勉強のペースが上ってきた。
昨年の末に社会学、心理学、介護概論の全体像を押さえ、昨日からは公的扶助論、社会保障論、児童福祉の過去問を解いている。社会福祉学は全体が一つの体系として繋がっているので、一度全体の形が見えてくると後の勉強は楽である。
今日は家族を連れて春日部市内にある八幡神社へ出掛けた。とりあえずというか一番大切な「交通安全」を祈願してきた。ハンドルを握る以上、気の緩みは禁物である。ただでさえ私は考え事をしてぼーっとすることが多いので気をつけたい。
と同時に、来月車検を迎えるミラージュをどうしようか迷っている。社会人になって初めて買った車で大変気に入っており、7年超えた現在でも絶好調なのだが、3ドアであるため、チャイルドシートを取り付けることができず面倒な思いをしている。子どもがこの先一人であることが確定しているならば、妻の4ドア(これまた厄介である)のワゴンRで事足りるのであるが、こればかりは何とも言えず困っている。
あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます
今年の元日は、今月末に控えた社会福祉士の国家試験の勉強でスタートしました。昨年は子供の誕生を控え落ち着かない中、大学の社会福祉士養成課程の現場実習から一年が始まりました。
今年は、3年間に亙った教育・福祉を巡る勉強や資格取得、実地の経験に一先ず区切りを付け、新しいことに挑戦してみたいと感じています。といっても、試験が無事終了し、スタート地点に立たないことには次に進めません。まずはスタート地点まで「猪突猛進」でしょうか。
初級シスアド
今日は松原団地駅に隣接する獨協大学で初級シスアドの試験を受けてきた。
当日の電車の中や昼食を食べながらの勉強も合わせて正味15時間くらいの勉強であったが、普段からパソコンに触れているせいもあってか、解答速報で午前8割、午後7割の点数をとることができた。初級シスアドとは、ユーザーの立場に立って、システム設計者と共同して企業の情報化の先導役を担う人のための基礎的な知識を問う試験である。そのため様々な数値や処理や販売、会計、成績、データベースなど日常頭を悩ます一連の処理を分かりやすく図示し、プログラム担当者に伝える情報整理能力が求められる。合否はともかく、DFDやE—R図、フローチャートで物事を図解したり、表計算の絶対値や関数、データベース関数の概要が整理できたりして勉強自体は面白かった。
初級シスアド合格のポイント(私見)
・午前問題は基礎知識が問われる。但し過去問からの出題が多いので、過去3年分春秋計6回ほどの問題を繰り返せばパターンは見えてくる。但し、ここ数年特にインターネット接続の技術革新が早く、最新の問題集を購入した方が良い。4、5年以上前の問題集だとISDNやダイヤルアップ接続など少し古い問題が混在されているので注意が必要。私は例のごとくブックオフで105円の問題集をやっていたので、余計な知識が付いてしまった。
・午後問題はIPアドレスや暗号技術、またSQL構文や表計算の関数の基礎的なところが理解できていれば、あとは文章理解能力が試されていると言っても過言ではない。時間が足りないので、過去問を解いて、設問の構成の特徴を理解しておくと良いだろう。
初級システムアドミニストレータ
先日、初級システムアドミニストレータの試験の申し込みをした。単なる基礎的なパソコンの知識を試す試験だろうと気軽な気持ちで申し込んだのだが、いざ問題集をやってみるとなかなか手応えのある問題が多いので戦いている。コンピュータの基礎やネットワーク技術の基本は簡単なのだが、データベースやSQL、経営工学的な視点からの問題に手を焼いている。本試験は10月中旬なので、今月には試験の概要を把握しようと思う。