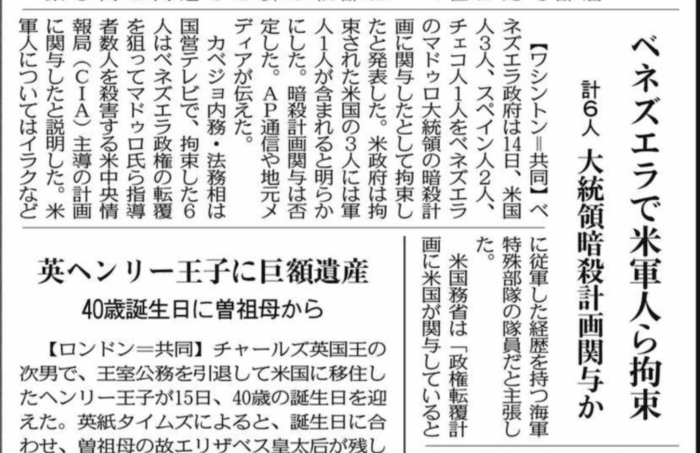室田武×赤星たみこ『わたしは趣味のエコロジスト』(メディアファクトリー,1993)を読む。
この手の環境に関する本は、「〜〜すべきだ」「〜〜を心がけよ」といった教条的な物言いが多く、ちょっとうんざりしながらページを繰っていった。しかし、本書はタイトルに「趣味のエコロジスト」とあるのように、日常生活の中で無理せずに継続できる形で、合成洗剤の使用を減らしたり、ゴミの分別を意識したりすることが大事だと述べる。
日本の場合、とにかく人間の排泄物というのが肥料として貴重な資源だったから、そもそも下水道を普及させる必要はなかった。しかし、明治になってなぜ下水が出てきたことかと、大雨のときに都市でよく洪水が起こったので、雨水を早く海に流すのが主たる目的であったそうだ。
西洋の国では、だいたい人糞を不浄視する考え方があって、それを農地にきちんと入れる習慣がない国もあった。フランスのパリでは農地に還元しないから街路の上にぶちまけたりして、これでは汚いし臭いがきついし、それで悪臭や伝染病を防ぐために下水道ができた。水は液体の時は空気より重いけど、期待になると空気より軽くなる。分子量でいうと、H2Oは18にしかならない。一報大気のN2の分子量は28、酸素の分子量は32ということで、28と32の重さのものが4対1で混じっている。それに対して水蒸気というのは18しか重さがないので、浮力が発生してどんどん上空に昇っていく。
水分を吹くんでいる空気はなんとなく重そうな感じだが、実際は軽いので上空へと上がっていく。日本の水田農業は理想に近い農業である。水田は山の養分をそのまま利用しているので、化学肥料をそんなに使わなくても7割くらいは穫れるはずである。ところが、大陸のヨーロッパでは、アルプスの周辺は別として、日本みたいに山岳地帯がないから山からの養分があまりない。ヨーロッパでは地力を維持するということで、連作障害が出ないようにして休耕する部分をかなり残しながら、近くに林を人為的に育てておいて、その落ち葉を入れる。だから、畑とその周辺の林を一体のものとして考えるのが三圃式農業である。