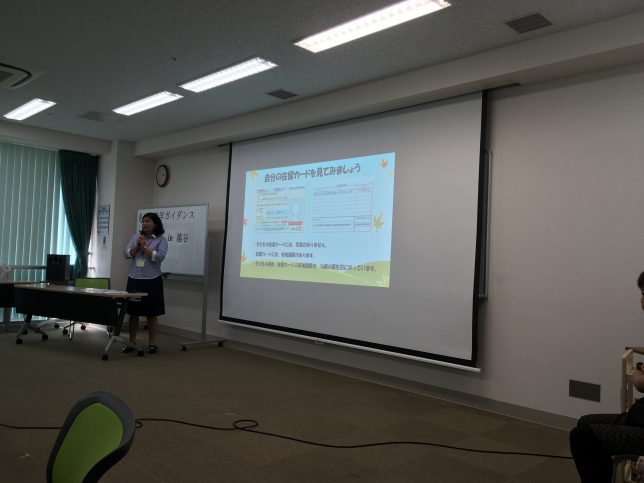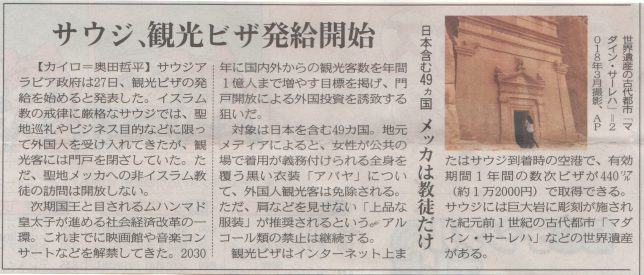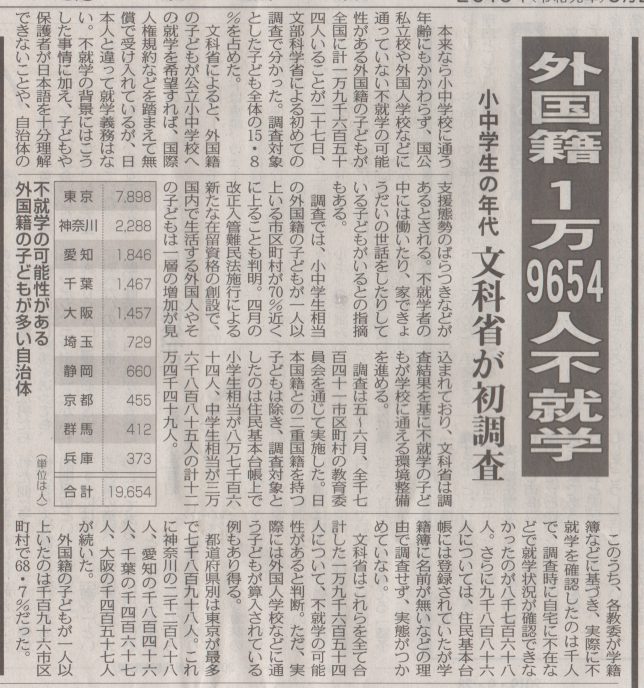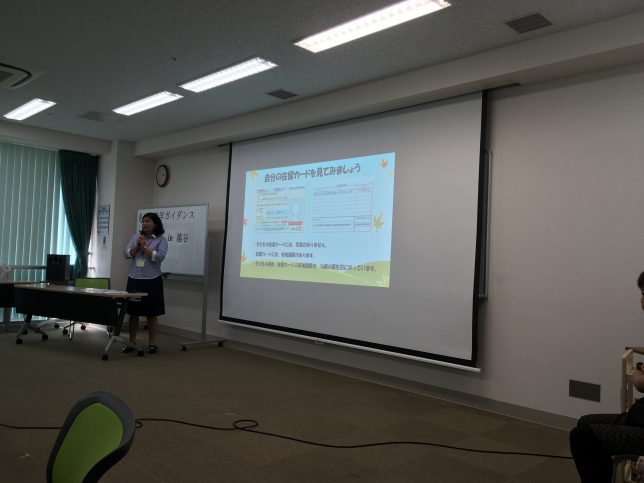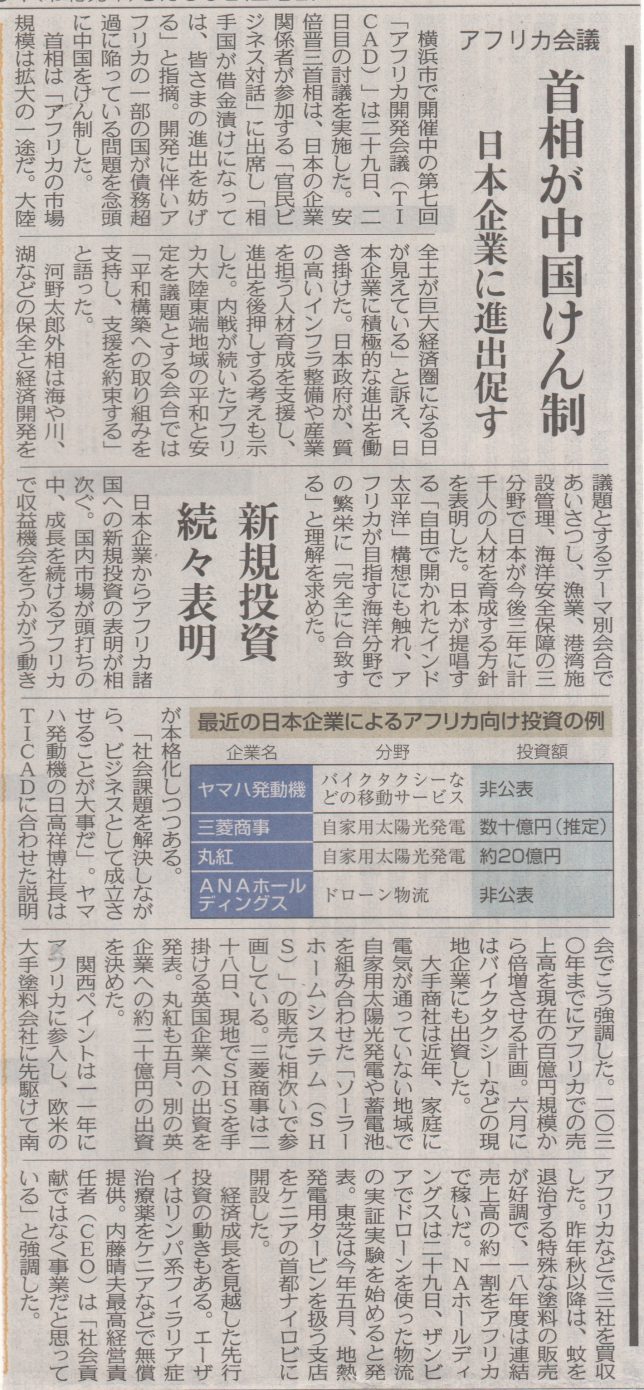本日,越谷で開催された「外国人のための高校進学ガイダンス」にアドバイザーとして参加してきました。かれこれ10年以上関わっているイベントです。
埼玉県の東部地区でも外国籍の生徒が増えています。中学校までは義務教育なので,日本語能力の如何を問わず,地元の公立中学校に通うことができます。しかし,公立高校に進学するには必ず高校入試を受けなくてはならず,日本語が出来ないと授業についていくことができなくなってしまいます。そこで生徒の日本語能力や保護者の考えも加味しながら,高校進学について通訳を介して説明していきます。
現在,埼玉県では12校の高校で,日本に来て3年以内の生徒を対象とした「外国人特別選抜入試」を行っています。埼玉県東部では草加南高校,三郷北高校,川口東高校などです。また,吉川美南高校や越ヶ谷高校には定時制が設置されており,日本語を学びながら勉強する場もあります。一人ひとりの将来の目標などを聞きながら,勉強方法などを伝えていくのですが,高校生の2者面談や3者面談のような雰囲気で,気疲れもしますが楽しい時間でした。
しかし,高校と大きく違うのは,外国籍の生徒なので,在留資格が関係してくることです。家族状況や日本に来た年齢でも変わるのですが,日本の高校を卒業し,その後進学や就職をすることで,日本に永住できる権利を得ることができます。また,ネパールやパキスタンなどは日本と中学校の制度も大きく異なっているので,すんなりと日本の高校受験の資格が得られるわけではありません。
今後ますます,日本に住む外国籍の方が増えていきます。そうした中で,このような説明会は,高校教員として関わることができる国際交流のひとつだと考えています。通訳なしで直接生徒に語ることができれば,もっと親身に相談に乗ることができるのですが,その点が残念でなりません。今回,中国語,タガログ語,スペイン語,ポルトガル語,英語を母語とする生徒が参加していました。
皆さんも,ぜひこれらの言語を学んで,いつか一緒に説明会に参加しましょう。