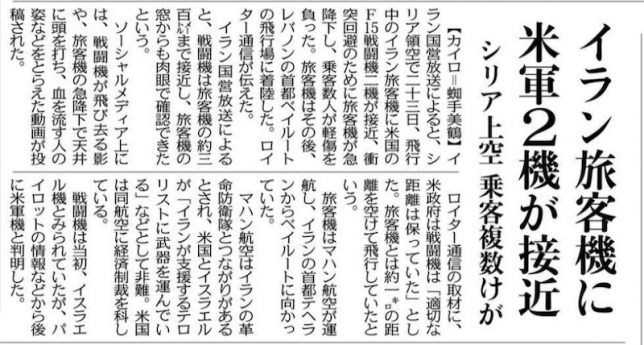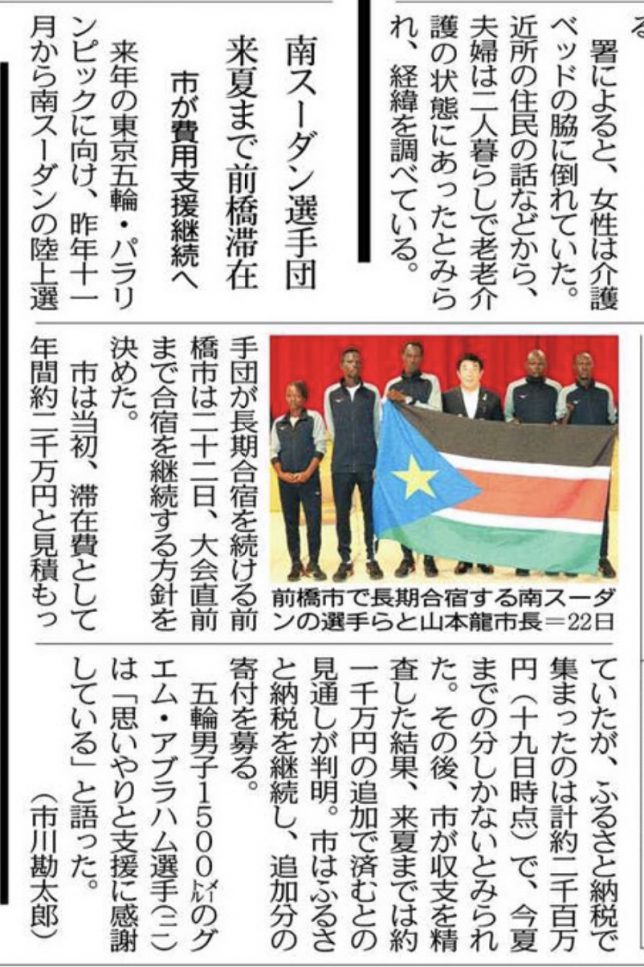本日の東京新聞朝刊より転載。
新聞だけでなくテレビでも米中問題が大きく取り沙汰され、株価や為替も大きく変動しています。米中のいざこざは、トランプ大統領就任後ずっと続いています。流れを押さえていくと、トランプ大統領は、米国の知的財産や特許技術が中国に盗まれているということを一貫して主張しています。
1970年代以降、東アジアや東南アジアの多くの国で、日本や米国の技術を活用した重工業の発展を経済政策の中心に据えていました。アジアNIEsやASEANなどの言葉を聞いたことがあるでしょう。中国は1990年代まで発展途上国だったのですが、安価で豊富な労働力を背景に「世界の工場」として、一気に先進国の仲間入りを果たしてきました。
中国は共産党が管理する国家なので、外資系企業が自由に中国で現地法人を立ち上げることはできません。中国企業と合弁会社を立ち上げる必要があります。また出資比率は50%を超えることはできず、事実上中国政府の言いなりとなってしまいます。それでも他国に比べ各段に人件費などの固定費が安かったため、世界中のブランドが中国に進出してきました。
但し、良いことばかりではありません。撤退の際には、合弁会社として保持していた技術情報の大半は、すべて中国当局に接収されてしまいます。中国はそうした先端技術を国レベルで蓄積していき、IT企業を中心に世界に打って出るようになりました。トランプ大統領の批判もそうした流れの中で理解すると良いでしょう。
トランプ大統領もコロナ禍で失点したので、お得意の「アメリカファースト・中国悪者説」で支持率を回復しようとする魂胆が見え隠れしています。昨年までは貿易が焦点だったのですが、今年に入ってからは、香港やチベット自治区、新疆ウイグル自治区などの政治問題・人権問題で中国政府に揺さぶりをかけています。
米中に挟まれた日本としては、どちらに対しても不必要に加担することなく、批判すべき点があれば、両大国に物を言えるポジションを確保しておきたいところです。韓国や台湾、オーストラリア、ASEAN諸国との緊密な外交戦略が求められるところです。
いよいよ2学期から東南アジアに入っていきますが、教科書の内容をなぞるだけのつまらない授業は止めましょう。米中の確執に割って入る、第3極としての東南アジアの可能性に言及できたらと思います。
また、生徒の皆さんには、大学や専門学校での専攻を問わず、使える英語の勉強をしてください。1日2時間は英語の勉強に充ててください。