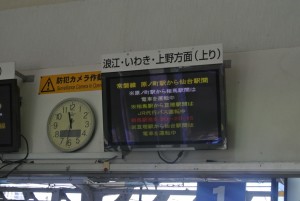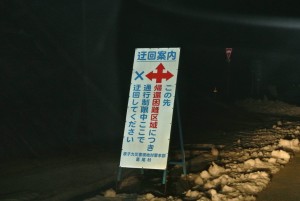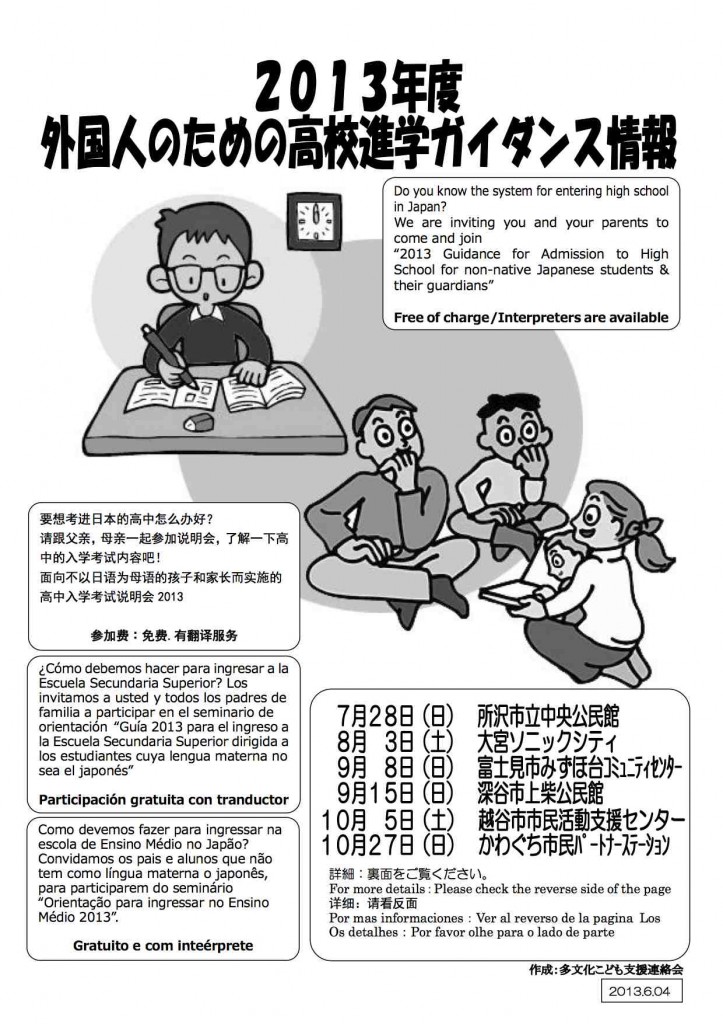一昨年の冬は福島第一原発の南側と岩手宮城の海岸沿いをぐるっと回ってきた。昨年は関東で唯一津波の被害に遭った千葉県旭市の港を訪れた。今年の後半以降、オリンピックやアベノミクス、その他の雑多な報道で、東日本大震災と原発事故のニュースが徐々に減ってきている。日本人はすぐに過去を忘れてしまう。そこで、もう一度被災地の現状を目に焼き付けて、これから考えるべき事柄を整理しておこうと東北を軽自動車で駆け抜けてみた。

野田の芽吹大橋近くの農道にある大型車の車止めを通っていった。神社の鳥居ではないが、通るたびにちょっとだけ別世界に行くような気がするお気に入りの通りである。



2013年12月現在、全ての原発が停止状態となっている。とりあえず、春日部から近い一番近い東海村原発に向かった。何を目標に進もうか案じていたところ、地図を見ると東海原発の近くに科学館があるではないか。常磐道を降りて国道245号を真っ直ぐ進んだ。しかし、残念なことに耐震補強のため休館であった。



東海原発の北側、豊岡海岸から原発の建屋を眺める。写真では少し分かりにくいが、海岸近くにあるにも関わらず、たった数メートルの高台に位置しており、6メートルに津波にも耐えられる防潮堤が設置されているが、東日本大震災並みの津波が押し寄せたらひとたまりもないであろう。


東海原発のすぐ近くにある東海村立白方小学校。大学と見間違えるような立派な建物である。電源三法交付金によるものか、東海村教委のモデル校かなのかは分からない。ただし、生徒が多数集まるような地域環境ではなかった。

東海村役場の正門から。村役場にしては立派な建物である。

東海村より国道349号線をずっと北上した。茨城県常陸太田市、福島県矢祭町、塙町、鮫川村と一気に走り抜けて、田村市小野町のセブンイレブンでカップラーメンを啜る。時計を見ると午後5時過ぎ。南相馬市まで一気に行けば駅前ホテルに泊まれるだろうと勝手な推測のもと、10万分の1の地図とにらめっこして福島第一原発から半径20キロ圏外の近道を探る。そのまま国道349号線を進み、県道50号線に入った。


県道50号線を進み田村市を東へ抜けていく。途中田村市船引町付近は電飾でピカピカであった。行きは意味が分からなかったが、1時間後に帰る際はその暖かさが伝わってきた。

田村市の東にある葛尾村は村内全域が警戒地域にあたっており、全村民が村外に避難をしている。防犯のためか、パトロールの車がずっと村内を走っていた。国道399号線を北に抜けようとしたが行き止まりであった。仕方なく元来た道を引き返すことにした。
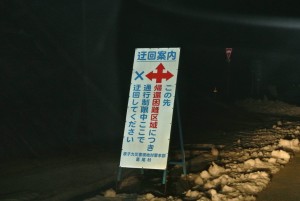

民家をよく見てみると、通りの全ての住宅に「除染完了部」という札が掛かっていた。信号以外に全く明かりのない闇の世界であった。帰りに田村市の電飾を見ると、人間の住む世界に帰ってきたような気がしてほっとした。その後、国道459号線を抜けていこうとするも行き止まり。途中タイヤチェーンを付けたり外したりで疲労も蓄積。結局国道114号で福島駅に向かう。駅前のホテルで一泊。