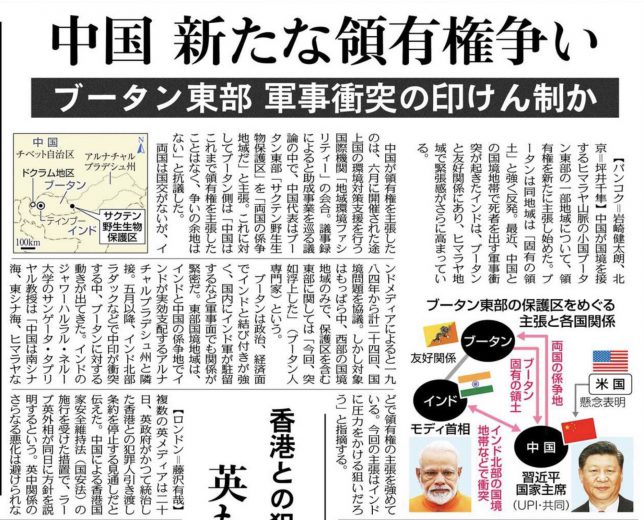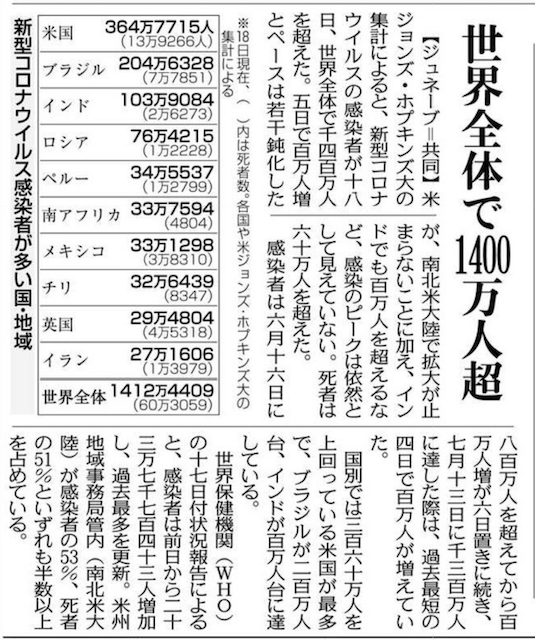五木寛之『金沢望郷歌』(文藝春秋 1989)を一気に読む。
ひさしぶりに五木寛之氏の小説を堪能した。高校時代に読んだことがあるのかもしれないが、全く覚えてはいない。
主人公は40歳を過ぎた金沢の地方タウン誌の編集長で、人生のレールが敷かれつつも迷ってばかりいる40代という、人生の踊り階段で繰り広げられるドラマが展開される。雑誌「オール讀物」に1年半にわたり四回に分けて連載された作品で、どの章立ても一つの作品としてまとまりがありつつ、全体のバランスも取れている逸品となっている。
久しぶりに良い小説に出会った心地よい読後感を味わうことができた。五木寛之小説のベスト5に入る作品であろう。では残りのベスト5は?