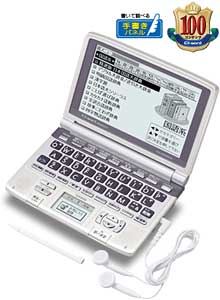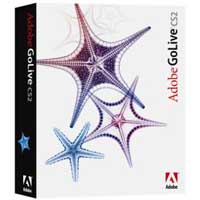ぶらっと近所の本屋に行ったついでに、埼玉県で高校入試対策の業者テストを一手に行なっている北辰テストの案内パンフレットをもらってきた。埼玉県内の中学生の9割以上が受検する模試の業者である。私学側の必要以上の協力も得られるためか、パンフレット自体は、20年前から全く変化のないような官公庁の出す案内のようなものであった。ベネッセやZ会といったCMで名前が知られている大手ではなく、埼玉県民以外全く名前の知られていない業者に、県の高校入試制度そのものが振り回されているという現実は看過できないものであろう。
しかも、成績優秀者は会報『前進』に氏名が紹介されるという。『Z』会の会報誌に名前が載るというのも生理的に嫌なものだが、『前進』なるものに名前が掲載されるのは「頭身の毛も太る」というものであろう。
「学習・学び」カテゴリーアーカイブ
電子辞書
先日、職場で3〜4年ほど愛用していた電子辞書を失くしてしまった。仕事にも差し支えが生じるし、英語の勉強にも不便を来していたところだ。
これを期に様々なコンテンツが入っているもっと性能のよい辞書が欲しくなり、新しく電子辞書を購入する運びとなった。そこで、インターネット上を物色しているうちに、国語学界の権威であらせらる「日本国語大辞典」が収録された電子辞書があるとの情報を得た。そして、その辞書の存在を確かめるや否や、突然にここ数ヵ月忘れかけていた学問意欲が心の内奥から湧出し、この辞書を活用した博学な学究生活が眼前に現出してしまい、ふと気付いたらポチッとネット通販の注文の手続きを終えていた。
カシオのXD-GW6900という最新機種の一つ前のタイプで、しかも展示品ということで2万2千円で買うことが出来た。日本国語大辞典だけでなく、日本語類語辞典や百人一首、ブリタニカ国際大百科事典などあれやこれやで100近くの辞書、辞典類が収められているので、一日中見ていても飽きない。バックライトも付いているので、昨夜は布団の中でもポチポチと画面とにらめっこ状態だった。
GoLive終了
先日のエルゴソフトの「EGWORD」の販売・サポート終了に続いて、現在このウェブを作成している「GoLive」というAdobeのホームページ作成ソフトまで開発・販売が終了してしまった。現在使っているGoLive CS2は大変バグが多く、すぐにフリーズしてしまって手を焼いていたので、次のバージョンを購入しようかどうか思案している最中の販売終了であった。テストの作成用にEGWORDを、ウェブ作成用にGoLiveを使いたいがために、これまでMacを使ってきたのであるが、これでMacを使う積極的な理由は見あたらなくなった。さてWindowsに乗り換えるか、それともスタイリッシュなMacBook Airを手に入れてDREAMWEAVERを活用したマックライフを満喫するか。さあどうしようか。
「国技・相撲」—近代以降の事件と名力士—
以下、私の友人が主催した企画です。
〈開催中の常設展示〉
第153回常設展示 「国技・相撲」—近代以降の事件と名力士—
日本の国技と呼ばれる相撲。その歴史は長く、古くは『日本書紀』にも記述されています。
しかしながら、「国技」と呼ばれ、スポーツとして扱われるようになったのは、明治以降のことです。西欧化のすすむ中、「蛮風」とされ存亡の危機にさらされた相撲は、制度の改善や「国技館」の設立等を経て近代的なスポーツとしての形を整えていきました。
今回の展示では、近現代の相撲の歩みを、『事件』と『ひと』の二つの観点から取り上げます。
相撲の組織や制度の近代化を推し進めるきっかけとなった、力士の処遇をめぐる事件や、マスメディアの発展によって誕生したスター力士たちの活躍を通して、今や日本を代表するスポーツの一つとなった相撲の歴史をご覧ください。
展示期間
平成20年4月17日(木)〜平成20年6月17日(火)
(利用時間・休館日をご確認ください)
展示場所
東京本館2階 第一閲覧室前
□ 国立国会図書館 東京本館 常設展示 □
「日本語を母語としない子どもと保護者の高校進学ガイダンス」
本日仕事の関係で、埼玉県越谷市で開催された「日本語を母語としない子どもと保護者の高校進学ガイダンス」という進学ガイダンスに参加した。世界一難しいと巷間指摘される日本語のハードルに阻まれ、高校への進学、さらには大学進学、将来の夢すらも見据えることができない中学生に、入試や学校選びのアドバイスを行った。
日本への出稼ぎや国際結婚など様々な理由で日本へやって来る子どもはここ20年で確実に増えてきている。県教委の話によると、日本語が十分に使えない外国出身の生徒は各中学校に2〜3名、埼玉県全県で少なくとも数百人近くいるということだ。親や社会の一方的な都合で母国を離れざるを得なかった子どもに高校教育の場にチャレンジする適当な機会を設けることは、県として当然やるべき責務である。
確かに定時制高校や競争率1倍を切っている高校に入ることは、少子化の現在容易なことである。しかし、日本語のサポートや取り出し授業、その他の支援体制が組まれた学校は少ない。普通高校教育の現場においても、ますます多国籍化していく生徒の実態を踏まえ、「特別支援教育」的な考え方が必要になってくるであろう。
〈特別支援教育についての文科省の定義〉
「特別支援教育」とは、障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うものです。
平成19年4月から、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において、障害のある幼児児童生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。
主催:財団法人 埼玉県国際交流協会
埼玉県総合政策部国際課