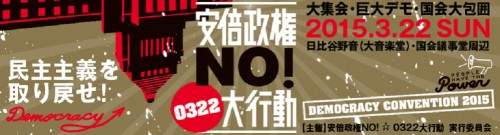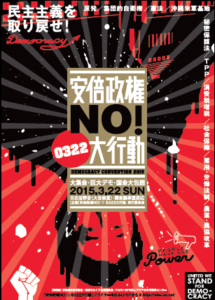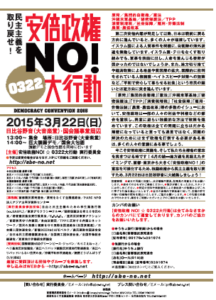先週発売された「サンデー毎日」(2015/07/12)に憲法学者小林節氏の小論文が掲載されていた。
小林氏は、安保法制における「後方支援」という政府の言い分のデタラメさを指摘し、国際法上の集団的自衛権の行使が明白に違憲であると喝破し、憲法解釈の変更による新安保法制を「裏口入学」だと断じた上で、堂々と憲法改正を目指すべきだとし次のような新9条を提案している。
1項 わが国は第二次大戦の経験を反省し、二度と間違っても侵略戦争はいたしません。これを世界に誓います。
2項 ただし、わが国も独立主権国家である以上、わが国が侵略の対象とされた時には、堂々と自衛戦争を行う。
3項 そのために我々は自衛軍を持つ。
4項 この自衛軍を用いて、国際貢献を行うが、それは国連安全保障理事会の決議がある場合に限る。
かつての自民党や最近までの民主党の考え方に近いもので、「自衛戦争」や「自衛軍」という言葉に敏感に反応してしまうが、安倍総理のゴリ押しする、敵を作りテロを誘発し戦争を拡大するための新安保法制と照らし合わせると、極めて真っ当なものに感じる。
子どもがまだ小さく、国会前の反対闘争に馳せ参じることは難しいが、現場に出向いて声を上げること以外の「後方支援」を積極的に行っていきたい。