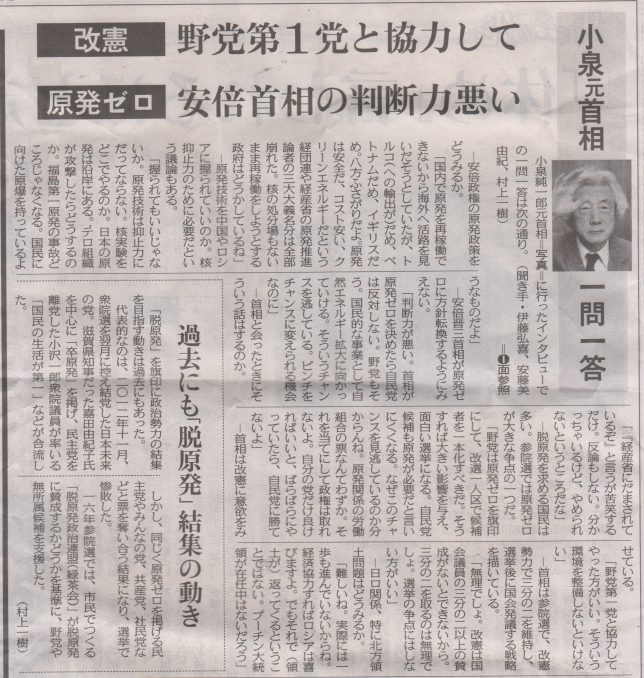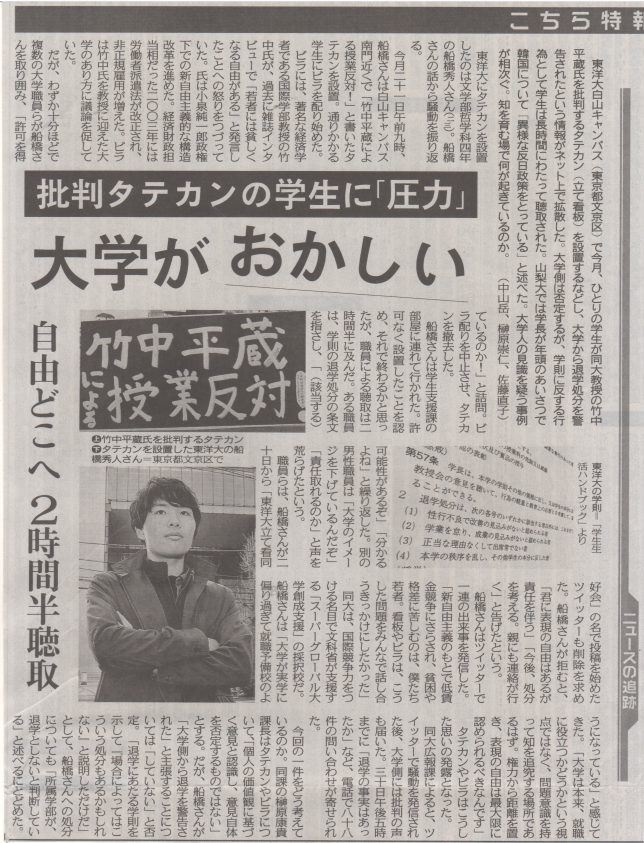本日の東京新聞夕刊に,米下院の民主,共和両党の超党派議員が「中国政府による新疆ウイグル自治区での過酷な人権侵害に対して米政府は何もしていない」と批判し,人権侵害に責任のある中国政府に制裁を科すなど対中圧力を強化するよう求める書簡をポンぺオ国務長官に送ったとの記事が掲載されていた。
書簡の中でウイグル族を「再教育」するための収容キャンプに大勢の住民が送り込まれていると指摘し,「事態は緊急を要する」として,行動を急ぐようトランプ政権に要求している。
また,中国での信仰の自由を求めるイスラム教やチベット仏教などの団体は,米首都ワシントンの議会庁舎で記者会見を開き,宗派を超えて中国政府の弾圧に抵抗し,米政府に行動を求める「中国宗教自由促進連盟」を立ち上げたと発表している。
こうした,中国政府による人権侵害,宗教弾圧に対しては,経済封鎖や司法裁判などで周辺国が一致協力した体制を作ることができなければ功を奏しない。米中2大国体制の昨今,米政府に頼るというのも理解できるが,アジアの中で声を挙げて批判していく国が必要である。経済を慮るばかりに,政治が停滞してはいけない。中国政府の目も余る横暴ぶりに括目していく必要がある。