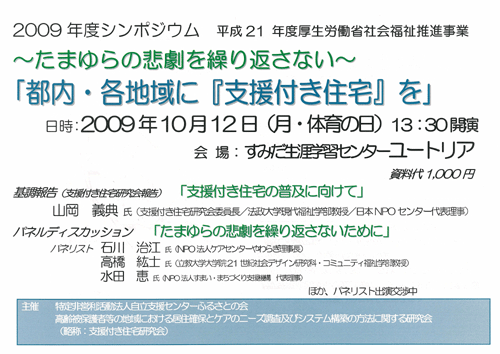今日の東京新聞夕刊に、京都市立堀川高校長の荒瀬克己さんのインタビュー記事が掲載されていた。
堀川高校は堀田力氏や葉加瀬太郎氏などを輩出した伝統校である。荒瀬氏が98年に教頭として赴任して以来、生徒がテーマを決めて研究、論文にまとめる授業を取り入れる改革が始まり、その結果、最難関大学に数十人の合格者が出るようになり、「堀川の奇跡」と呼ばれている。
発言の一つ一つが大変印象に残った。
高校は大学の予備校ではないという反発もあった。高校は義務教育から続く教育の完成でもある。集団の中で個を磨くのは高校まで。高校三年の最後のホームルームは人生で最後のホームルームでもある。
例えば堀川では文化祭を三年生含めて二カ月も準備をしてやる。生徒たちはいいものをつくろうと毎日遅くまで残る。そうした集団の中で個が成長していくことにつながる。行きたい大学があればそこへ行って勉強するのも大切な幸せで、教師としてはかなえてやりたい。結局よく学びよく遊ぶのが大切なのです。
生徒に接するときには何を考えていますか。
生徒には生徒の都合があるということ。生徒の価値観、考えを無視する形で指導しても納得してもらえない。そして生徒と話をする。問いかけが大切。生徒は本人も知らない力を内包している。それを気づかせるきっかけの一つが問いかけ。もうひとつは大人の姿勢を見せること。どういう場面でどういう判断をするか、生徒に見られている。それを意識しないで生徒に接するのは怖いですね。堀川高校の常任講師のあと、市立工業高校に国語教師として勤めていた時のこと。古典の文法の時間に生徒から「これやってなんぼになるんですか」と聞かれて、きちんと答えられなかった。工業高校なので機械の勉強などは将来の役に立つ。文法の授業はそうした意味では役に立たない。「知らないことを知るのはいいことだ」と言うのが精いっぱいだった。今なら違う答えをする。「学ぶとは、分からないものに立ち向かう方法を身につけることだ。文法の授業もその方法の一つだ」と。