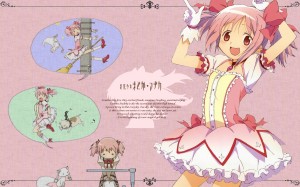近所のTSUTAYAで新房昭之監督、虚淵玄脚本『魔法少女まどか☆マギカ』のDVD全6巻を借りてきた。
3日間で一気に全12話を観て、また第1話、第2話と繰り返し観ている。
「文化系トークラジオLife」でも評判になっていた作品である。第1話や第2話を見始めた際は、「萌え系」アニメのタッチに慣れず、「40歳のおじさんがはまるべき作品なのか」と疑問を感じながらの鑑賞であった。
しかし、回が進むごとに謎が明らかになってきて、どんどん作品の世界にはまり込んでいった。ちょうど学生時代に『エヴァンゲリオン』を観た時の興奮がよみがえってくるようであった。
たかが中学生の淡い奇跡への憧れから生じる悪夢を「自己責任」として処理してしまうキュウべえの考え方は、まどかが指摘しているように全うなものなのか。
人間の生の感動を単なる事象として回収してしまうキュウべえの考え方は、現在のビッグデータやマーケティングを象徴しているのか。
ひたすら自己犠牲を強いる魔法少女の世界は極めて男性的な論理で支配されているが、、その中でキョウコやホムラのように自分にわがままな女性的価値観こそが、現在のブラックな社会に必要なものなのか。
物語の謎は次々と解かれていくが、心の中の疑問は次々と膨れ上がっていく。
最終話になると、手塚治虫の『火の鳥』を彷彿させる展開に息が止まるようであった。
今、パソコンに向かいながら、第1話から確認のために見返しているのだが、今度は「鹿目まどか」を見守る「暁美ほむら」と私自身の視線が同一化してしまっていることに驚く。
早く映画版を観てみたい。そして眠い。。。