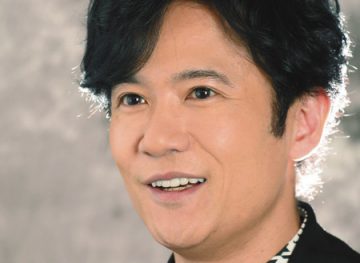本日の東京新聞朝刊に、哲学者内山節氏のコラム「時代を読む」が掲載されていた。
月1回ながら、現実社会の動きから少し俯瞰して問題点を提起している。相も変わらず分かりやすい文章なので、練習に書き写してみたい。
内山氏の指摘するように、感情的な物言いをする人を称賛するような雰囲気が、ここ数年特に強くなってきたように感じる。政治家や経営者だけでなく、芸能人やスポーツ選手も露骨に感情的なパフォーマンスを「演出」するようになった。つい先日も、トランプ大統領を真似したのか、日本のクジラ肉食文化が理解されないと、国際捕鯨委員会(IWC)を脱退する旨の発表があった。捕鯨の是非はさておき、国際的な議論の場を抜け出すというパフォーマンスは頂けない。議論は尽くすものであり、逃げるものではない。感情を露わにすることが、素直で正直な人柄だと受け取ってしまうネット社会のムードに少し注意が必要だ。
インターネットが普及しはじめたとき、それは世界を変える夢の道具のように言われたものだった。世界中のどこからでも、誰もが発信できる。情報発信では大都市と田舎の格差はなくなり、国境を越えた世界市民の時空が広がっていく。こんな解説をしばしば耳にしたものだった。人々の間を正しい情報が行き交い、理性的な議論の場がつくられていくことが、インターネットに期待されていた。
だが、期待通りにはいかなかった。むしろ、自分の感情にもとづいて発信し、自分の感情に合うものを検索する、感情のための手段としての利用が広がっていった。
それは世界に、無視できない変化を与えたのかもしれない。なぜなら、自分の感情だけを判断基準にして行動する人々を、大量に生みだすことになったからである。少し前までは、感情よりも理性が重視される時代だった。感情だけでものを言うのは、恥ずかしいことだとされていた。ところが感情よりも理性が上に立つと、理性的な意見を述べるための作法に習熟していない人たちは、社会から疎外されていく。「知的」な議論をするための素養が必要になり、それが「エリート」の支配を生みだしてしまうのである。理性重視の時代は、自分は社会の主人公にはなれないと感じる、大量の人々を生みだしてしまっていた。
近代的な世界では、たえずこのことへの不満をもつ人々がいた。政治も思想、理念、メディアを動かしているのも「知的エリート」たち。そういう構造への不満が、社会の奥には鬱積していたのである。
インターネットは、このような構造からの「解放」をもたらした。「知的エリート」に支配されることなく、自分の感情をそのまま発信できるようになったのである。感情を判断基準にして行動する人々がふえ、それが深刻な感情の対立を広げていく、そんな世界がここから生まれた。
アメリカのトランプ大統領を支えているのも、けっして少数派とは言えないアメリカの人たちの感情だ。日本でも中国になめられるなという感情、北朝鮮や韓国に対する感情などが安倍政権を支えている。その中国や韓国もまた、「国民感情」が大きな力をもっている。ヨーロッパで台頭する国家主義勢力の基盤も、いまの状況に不満を持つ人々の感情だ。
社会への不満やいらだちがそのまま発信され、それがおおきな渦となって社会を動かす。政治は、それを助長する扇動政治の性格を強めていく。
今年は、世界はいまこのような方向に向かっているのだということを、より明確にした年だったのかもしれない。感情の対立がそのまま容認される時代が、私たちを包んでいる。
とすると現在私たちは深刻な課題を背負わされていることになる。むき出しの感情対立が世界を動かすのが、よいはずがない。だが、理性が支配することがよかったのか。近代社会は、理性による秩序づくりをめざした。それが近代の理念だった。だがそれは理性的であるという規範を牛耳る人たちの支配を生み、「エリート」と主人公にはなれない人々の分裂をつくりだした。
おそらくこの対立は、普通の人々が社会の主人公になる仕組みが生まれないかぎり、解決されないだろう。理性による支配ではない協同の仕組みを、私たちは見つけ出さなければならなくなった。