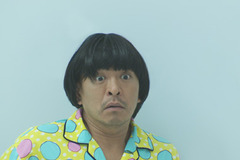本日の東京新聞夕刊の文化欄に精神科医の野田正彰氏へのインタビューが掲載されていた。
第二次世界大戦中、日本がアジアの人々を虐げた事実を告発し、今なお被害に苦しむ人の叫びをとりあげた近著『虜囚の記憶』(みすず書房)についてのやりとりである。
著書の中に次のような記載がある。
侵略戦争についての無反省だけでなく、戦後の六十数年間の無反省、無責任、無教育、歴史の作話に対しても、私たちは振り返らねばならない。戦後世代は、先の日本人が苦しめた人びとの今日に続く不幸を知ろうとしなかったことにおいて、戦後責任がある。
そして、著者は記者の問いに次のように答える。
日本の社会全体が、過去を見つめるというのがどういうことか分かっていないですね。個人のことに置き換えれば、自分がなぜ失敗したのかを考えることは大事だとみんなが言います。でもそれが社会のことになるとなぜ”否認”の方が価値があるのか。
そして、野田氏は読者に次のようなメッセージを伝えている。
社会というのは広い意味で文化を継承していますから、文化を変えていくにはよほどの努力をしないといけない。自分の生きている社会が行ってきたこと、しかもそれを反省せずにいるのに連綿とつながって、自分もまたその中で教育を受けて生きている。それに気付かない限り、平和の 問題を自覚するのは難しいというのが、私の経験に基づく一定の結論です。