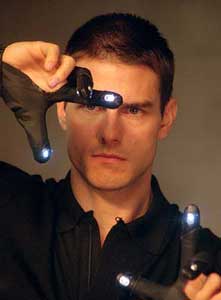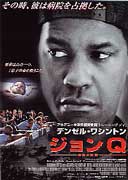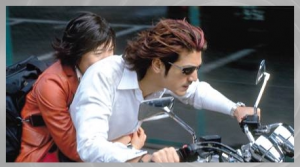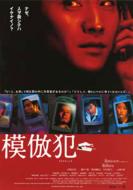本日トムクルーズ主演・スピールバーグ監督の『マイノリティレポート』(20世紀フォックス 2002)を観に行った。
『ミッションインポッシブル』と重なっている場面もあったが、伏線が何本もあり最後まで展開が読めず面白かった。情報ネットワークのデジタルな社会とアナログな人間感情の矛盾というシンプルなテーマのSF映画なのだが、市民のプライベート情報のデータ化や推定有罪に基づく予防社会など、現在の社会状況をうまく延長させた世界が展開されている点が不気味に感じて仕方がなかった。ジョージオーウェルの『1984』の現代版と捉えると、興味深い味わい方ができるはずである。
「映画」カテゴリーアーカイブ
コメントを残す
『ジョンQ』
先日、ニック・カサヴェテス監督のアメリカ映画『ジョンQ』(2002 米)を観にいった。
金のかかっていない映画であったが、なかなか面白かった。デンゼル・ワシントン演じるジョンQが息子の心臓移植リストへの登録を要求するために、病院を占拠するわけだが、舞台劇を観ているような生々しさを感じた。
また面白いことにチェーンで占拠された病院内ではベテランの医者と新米の医者と患者と患者の家族の関係性が崩れていくのだ。そして新米の医者の口から貧乏人を救わない医療保険制度の欠陥が語られ、ベテランの医者の口からは医療体制の矛盾が語られる。ちょうど全共闘でのバリ封内での解放区のような議論が展開される。結局ジョンQは犯罪者として罪に問われるのだが、それはそのままアメリカの医療保険制度の不備を指摘するものであった。