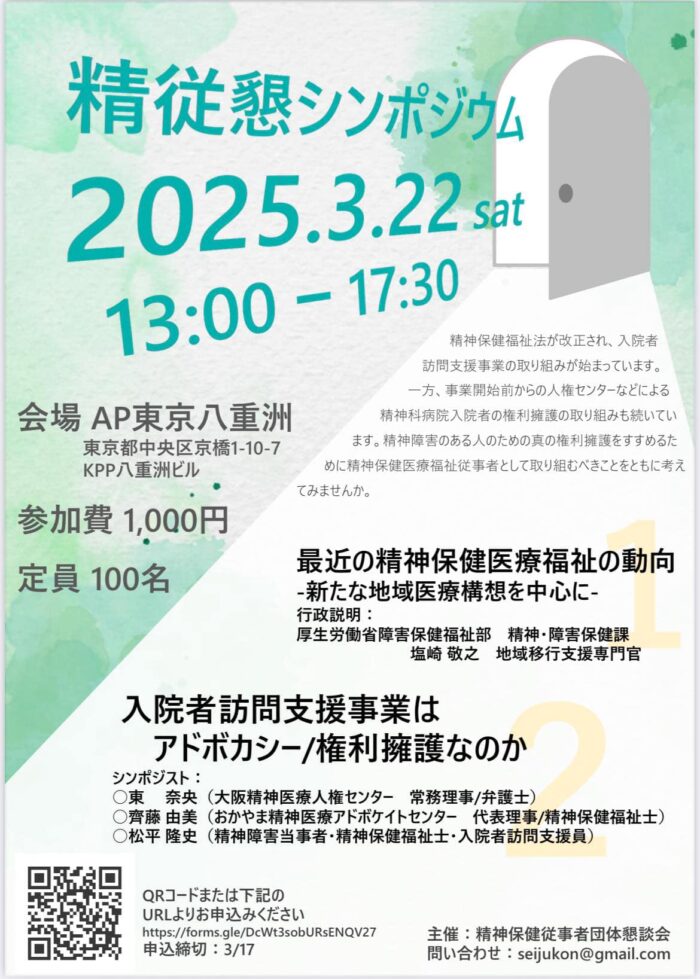分会報告続々
4月12日、武蔵浦和コミセンで、各学校の代表が会した、今年度最初のくじら会議が行われた。冒頭、羽田委員長より、働き方改革の掛け声が喧しくなる一方で、教員不足の対応が現場丸投げになっている現状が報告された。続いて、新任式での情宣の様子や給与改定及び共学化の意見交換会などの県教委の情報、国会での給特法の議論、日教組の動きなどが紹介された。
各分会からの報告では、小・中学校だけでなく、県立高校や特別支援学校でも教職員の未配置が顕在化してきた事例が報告された。また、前回の鯨波でも取り上げられたとおり、近年県立高校内に特別支援学校分校の設置が相次いでいるが、県立高校の教員の中には「高校側が主で、特支分校側が従」といった意識が蔓延しているとの報告があった。特支分校の教員や生徒が県立高校の校舎の間借りをしているような肩身の狭い思いをしており、早急の改善が求められる。また、校舎の鍵開け(朝7時半!)が教員の輪番で組まれている学校があり、校長交渉で早速改善に向けて動き始めた事例の報告もあった。
他にも、新採用の教員に分掌主任が振られるケースや、男女別学校での性差別意識の蔓延、教員間のパワハラ、新聞でも取り上げられた校歌・応援歌指導など、県教委との直接交渉が必要とされるような話題も多く寄せられた。
改めて勤務時間の服務規定の確認を
協議事項では、県が提示していた2024年度末までに時間外在校等時間が月45時間、年360時間を超える教員をゼロにするという目標が全く達成されなかった点について議論された。県は今年度新たに「学校における働き方改革基本方針」を提示したが、目標を示すだけで、実効策が伴わなければ、また同じ轍を踏むだけである。
中執から、校長交渉のポイントとして、勤務時間(1日7時間45分勤務で45分時間の休憩時間)や病休の扱い、勤務時間の割り振りなどの細かい取り決めの説明があった。過去の組合の先輩が中心となって勝ち取ってきたものである。組合と県教委の合意のもとに運用してきた制度を、現場の管理職が理解していないこともあるので、不審に思ったら組合に確認の連絡をお願いしたい。
会議の最後に、今年度退職された先生とくじら採用試験講座を利用して合格された先生方を祝うささやかな会が行われた。先生方の周りに埼玉県の教員を希望している方がいたら、ぜひ実績のあるくじら講座をご紹介いただきたい。