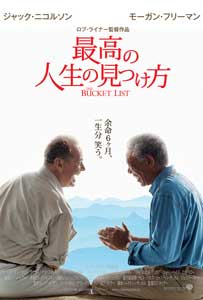2週間弱留守にしていた頃の新聞を読み返している。
8月1日付の東京新聞夕刊の匿名コラム「大波小波」に「アキハバラ後」と題した次のような文章が載っていた。少々過激な文章であるが、1971〜74年に生まれた団塊ジュニア世代の境遇を鋭く突いている。
『未来あるフリーター未来のないフリーター』(NHK出版、2001年)で村上龍は、「フリーターのことを心配しているわけではなくて、彼らの復讐がうざったい」(当時は製造業への派遣労働はなかった)と言っていた。その後「労働力需給の迅速、円滑かつ的確な結合を図る」ため、労働者派遣法が改定され(2004年)、就職氷河期の谷間に落ちた若者たちが工場でハケンとして働く現象が起きた。
これは規制緩和というイデオロギーに基づく政治的決定の結果であり、経済的な自然現象の如きものではない。「経済がそうなんだからしょうがない」とつい思いがちだが、あらゆる経済現象はあくまで政治的選択の結果だ。だから今日の労働者が置かれた事態には、これまでの為政者の責任がある。
希望のなさを殺人と結びつけたのは無論本人の責任だが、将来結婚して家庭をつくることもできない、一生工場と寮を往復するだけなんだ、とまで思い詰めさせたからには、何らかの形でテロルが続くことは避けられないだろう。だってこの社会は、彼らに「人生」を送らせないのだから、社会を破壊するという形でしか、彼らは生のエネルギーを放出できない。それにしても、刺す相手を間違っていると思うが。(朝日平吾)