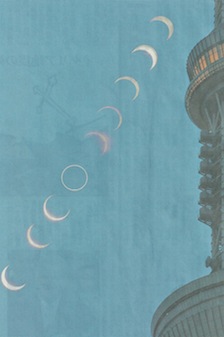本日の東京新聞夕刊に、「公立図書館サービス合戦」と題した記事が掲載されていた。
東京で公立図書館運営の民間委託が近年急増しており、23区では、計223館のうち182館(82%)で委託が導入されているという。民間委託によって従来の図書館になかったサービスが展開され、府中市では「図書館流通センター」に運営を委託し、蔵書83万冊にICタグを付けた新しい検索システムが導入され、年間貸出冊数が委託前の約2倍になっている。また、千代田区では「図書館コンシェルジュ」が置かれ、雑誌のバックナンバーが貸し出し中なら区内の古書店を紹介したり、観光案内などもしたりしてくれる。さらに、佐賀県武雄市は、ソフトレンタル店大手「TSUTAYA(ツタヤ)」を運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブに運営を任せる方針を発表し、年間1千万以上の運営費の削減効果を見込んでいる。
しかし、民間委託には反対の意見もあり、日本図書館協会の理事は「民家委託で職員は使い捨ての状態。利用者の幅広い読書要求に応じて資料や情報を提供したり、地域に根ざした蔵書の管理など、公立図書館が本来持つ役割を果たすことが難しくなっている」と指摘している。
図書館というのものは、短期的な指標ではなく、中・長期的なスケールで国民の利益に供するべきものである。単に年間の運営費や昨年比の貸し出し数の表面的な数値だけで、民間委託の是非の判断を下すのは早計である。
しかし、アマゾンのキンドルや、グーグルのサービスなど、著作そのものがデジタルの波にさらされ、既存の流通システムや法の目すらかいくぐろうとする現在、民間委託によりアナログの本の流通のシステムを守ろうとする「抵抗」はあってしかるべきであろう。