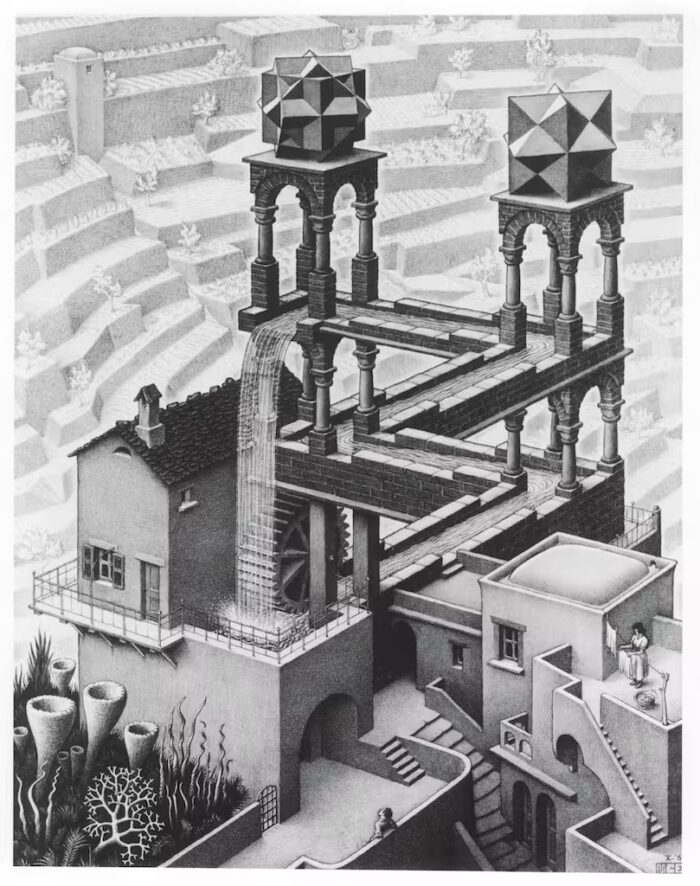安田淳一監督、山口馬木也、冨家ノリマサ、沙倉ゆうの主演『侍タイムスリッパー』(未来映画社,2024)を観にいった。
単館上映の自主制作映画であったが、評判に評判を呼び全国上映に拡大され、ネットやニュースで噂になっていた作品である。フィクションとノンフィクション、幕末と現代がそれぞれ重層的に進行しながら、絡み合い、そしてそれぞれの物語が成長していくという奇跡のような映画となっている。
また、ちょうど先月、会津若松城に行ったばかりだったので、会津藩出身の侍に想いを寄せてしまい、新撰組の活躍を描いた司馬遼太郎の『燃えよ剣』の感動もよみがえってきて、感動も一入であった。本当にいい映画に出会えることができた。観客それぞれに違った感動があるのだろう。もう一回観たい映画であった。