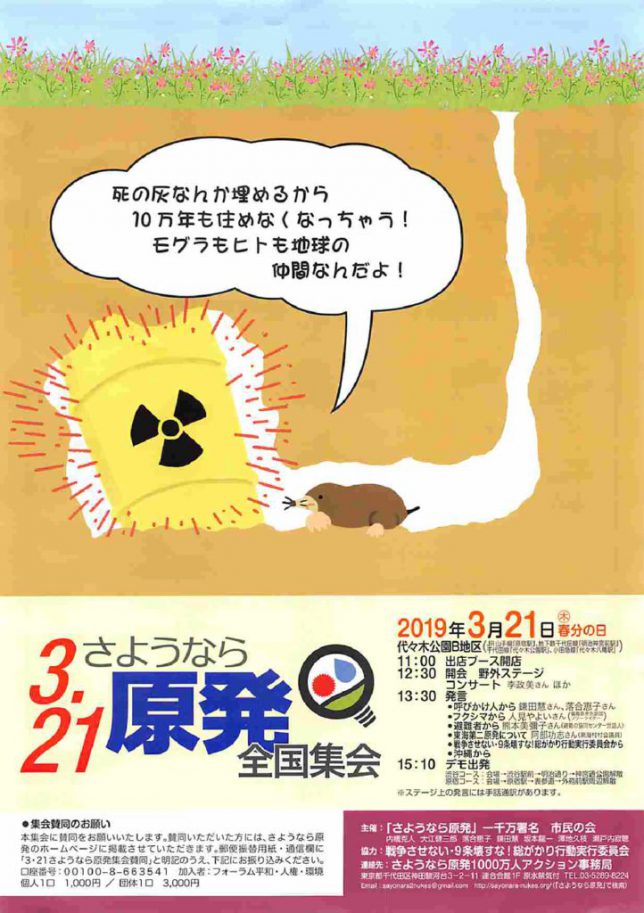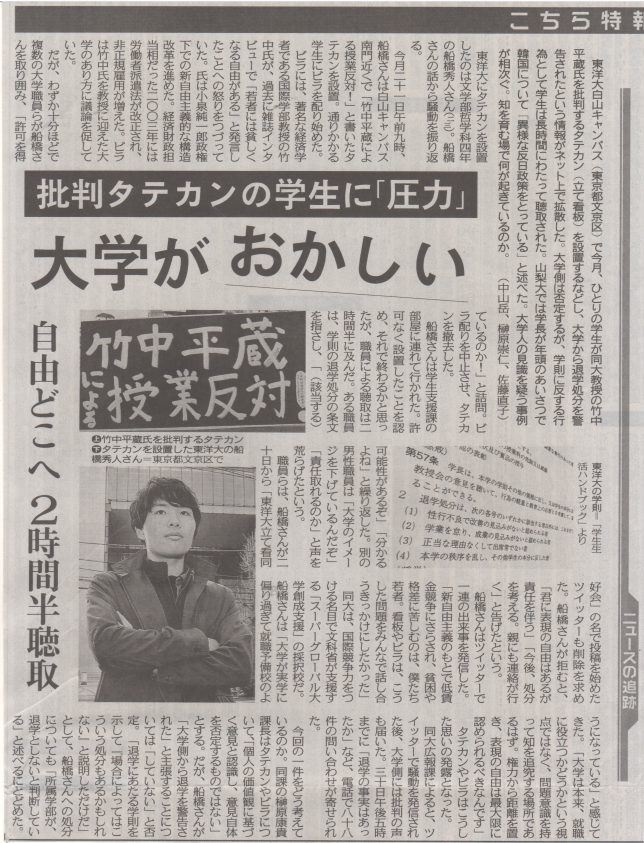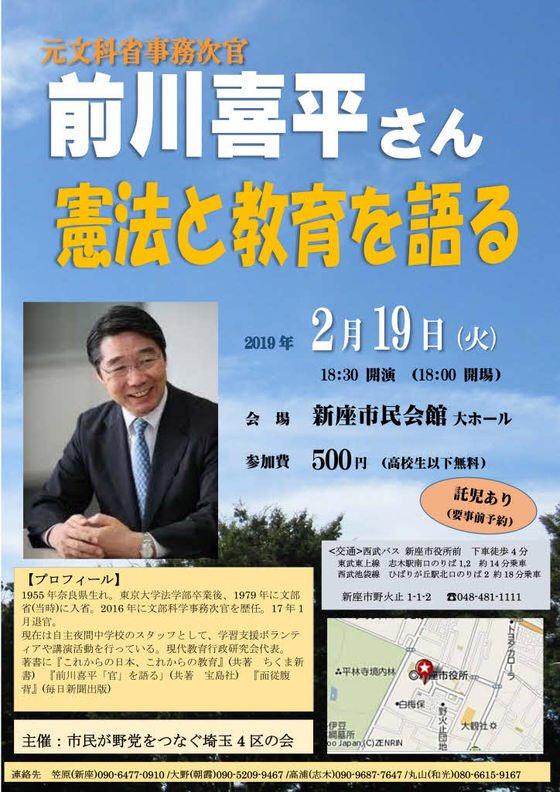組合のメーリングリストから転載
「社会運動」カテゴリーアーカイブ
「なぜ人々はヘイト本を買うのか 2・16講演集会報告」
救援連絡センターのメーリングリストから
2月16日、日本キリスト教会館において「なぜ人々はヘイト本を買うのか!2・16講演集会」が行われた(主催 差別・排外主義に反対する連絡会)。集会には75名が集まり、講演、質疑、連帯アピール、会場での交流会も含め、充実した取り組みとなった。
講師の倉橋耕平さんは1982年生まれで社会学。メディア文化論・ジェンダー論を中心に研究され、立命館大学等の講師を務め、著書に『歴史修正主義とサブカルチャー90年代保守言説のメディア文化』(青弓社)が評判を呼び、新宿紀伊國屋書店の人文書コーナーでこの1月、ベスト二位に選ばれるなど、今、注目の気鋭の社会学者である。
連絡会は今年で結成10年目を迎えるが、安倍政権が続くなかでヘイト、レイシズムの蔓延はますますひどいことになっている。この間、年に2回くらい講演集会やシンポを開催しているが、今回は、差別・排外を標榜する連中の背景には歴史修正主義が深く関わっていること、そうした言説に形や力を与えているのがメディアであること、そしてネット空間はもとより、街の本屋でヘイト本があふれている状況をいかに変えることができるのかという主旨で倉橋耕平さんにお願いした。
講演では、まず倉橋さんの関心の所在として、アカデミックの世界から距離を置かれているはずの歴史修正主義は、どこで、どのように展開されてきたのかに視点を据え、1990年代右派(保守派)論壇のなかで隆盛した歴史修正主義の特徴を具体的に指摘。右派論壇誌は90年代半ば頃から、「歴史」「中国」「韓国・北朝鮮」に集中し、そこに小林よしのりの『戦争論』(98年)が登場、大ベストセラーになる。この時期の右派論壇と歴史修正主義者たちは「ディベートと論破」にこだわる。それも歴史の事実・根拠を示すことはどうでもよく、その場の議論で主導権「を握れば良い。アカデミズムへの反発が読者参加型のサブカル空間を生み出し、ネトウヨ言説とヘイトたれながしの源流を形成する。一口に言えば「アマチュアの歴史による商業言説」であり、「参加型文化」と「共感」がポイントだという。倉橋さんは、今後の課題のヒントとして1956年に書かれたサルトルの『ユダヤ人』(岩波新書)から引用した。「彼等(差別者を指す)は、自分たちの話が、軽率であやふやであることはよく承知している。彼等はその話をもてあそんでいる〈中略〉彼等は不誠実であることに、快感をさえ感じているのである。なぜなら彼等にとって、問題は、正しい議論で相手を承服させることではなく、相手の気を挫いたり、とまどいさせたりすることだからである」。60年以上も前の言説であるが古くない。そういう意味で歴史から教訓を引き出すことはまだまだできると、その後の質疑も多くの質問が出され、交流会も含めて活発なやりとりが行われた。
連帯のアピールは、朝鮮学校無償化連絡会、APFS労働組合、終わりにしよう天皇制ネットワーク、沖縄への偏見を煽る放送を許さない市民有志、のりこえネットから、現在取り組んでいる課題の報告と提起がなされた。
今年は3・1独立運動100年で韓国では記念行事が行われ、東京でも2・24には屋内集会、そして3・1の当日には新宿東口広場でキャンドル行動とリレートークは日本第一党ら右翼の妨害を許さず勝ち取られた。天皇代替わり行事に抗う闘いにも連絡会として参加している。連帯・共闘を拡げていこう!
〝おわてんねっと〟からのお知らせ
以下,救援連絡センターのメーリングリストから
【2・24「天皇在位30年記念式典」反対銀座デモ】
日時:2019年2月24日(日)13時
集合:ニュー新橋ビル地下2Fニュー新ホール(新橋駅すぐ)
※政府主催の「天皇在位30年記念式典」
福島県知事が「国民代表」で天皇に感謝の辞をのべ、
明仁作詞・美智子作曲の歌を捧げるというとんでもない展開です。
明仁の30年なんて祝わない、祝えない!抗議しよう!
【3・30 天皇「代替わり」直前!今からでも“NO”と言おう集会】
日時:2019年3月30日(土) 13:15開場
場所:文京区民センター2F
※天皇制反対の集まりに参加したことのない皆さんも、
いない皆さんも大歓迎!
おわてんねっとが総力をあげて、
指摘します。代替わりに向けて、
★このほか、4/28~5/
乞うご期待!
【主催】終わりにしよう天皇制!『代替わり』反対ネットワーク(
TEL:090-3438-0263 mail:owaten@han.ten-no.net
ツイッター:「おわてんねっと」 web:http://han.ten-no.net/